室戸市 観光スポット
 |
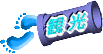 |
 |
室戸市のホームページヘ
室戸岬 室戸岬灯台 中岡慎太郎銅像 室戸青年大師像
空海の七不思議「鐘石」 御厨人窟 ビシャコ巌 天狗巌
あこう林 月見ヶ浜 弘法大師 行水の池 乱礁遊歩道 夫婦岩
ハイビスカス通り 室戸ドルフィンセンター
シレストむろと ホエールウォッチング
吉良川の町並みを歩いてみませんか!!
吉良川レトロな町並み“ 町並みお散歩ガイド!! ”
吉良川の町並み 吉良川の町並み館
室 戸 岬  室戸岬の海岸において、フィリピン海プレートの沈み込み帯に沿って起こる巨大地震によって引き起こされた大地の隆起の証拠を見ることができます。室戸半島に発達する完新世(約1万年前〜現在)の海成段丘は、繰り返して起きる地震時隆起の蓄積によって形成されたものです。室戸半島の地質と地形の研究は現在も進行中で、毎年、世界各地から多くの地質学者や地質学専攻の学生がこの地を訪れています。 ●場所 ・・・ マップ |
| 室戸岬灯台 白亜の灯台は室戸岬のシンボル  葵海と空に溶けこむように美しい、白亜の灯台。これは「日本の灯台50選」の一つに選ばれた、室戸岬のシンボル。明治32年(1899年)4月1日初点灯され、室戸沖を通る船の安全を願い、海を照らし続けてきました。当時の公費2万円、白色回転10秒間に1せん光、光源、1kwレンズを通すと190万カンデラ、光達距離約48km、ここからの眺望素晴らしく雄大絶景です。レンズの大きさは国内最大級の直径2m60cmです。毎年11月1日に近い日曜日には「室戸岬灯台まつり」を開催。前日の土曜日の夜(午後5時〜午後7時)と当日は、普段立ち入ることのできない灯台部が一般開放されています。 ●場所 ・・・ マップ |
 中岡慎太郎銅像 太平洋を見つめる龍馬の盟友 ・ 慎太郎 中岡慎太郎は、海援隊(日本の貿易会社)の坂本龍馬とともに明治維新に向けて活動した勤王の志士。慶応3年(1867年)11月15日、京都河原町の近江屋で龍馬とともに刺客に襲われ、志半ばで生涯を閉じた話は有名です。この時、慎太郎は30歳でした。のちの昭和10年、生誕地である安芸郡青年団が主体となって室戸展望台のふもとに銅像を建立。以来、室戸岬の先端に立ち堂々とした姿ではるか太平洋を見つめています。 ●場所 ・・・ マップ |
 室戸青年大師像 室戸青年大師像空海ゆかりのパワースポット 約1,200年前、19歳の若き空海(弘法大師)が修業の場として選んだのが室戸岬でした。波に浸食されてできた洞窟・御厨人窟(みくろど)に寝起きし、隣の神明窟(しんめいくつ)で、空と海だけを眺めて修行。難行苦行の末に悟りを開いたと伝えられています。そのためか、この洞窟には空海の霊力が宿るとされ、近年には心と体を癒やすスピリチュアルなパワースポットとして人気を呼び、数多くの人が訪れています。海のエネルギーや、室戸という土地が持つ不思議は力が感じられるかもしれません。 ●場所 ・・・ マップ |
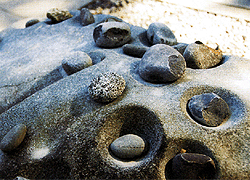 空海の七不思議「鐘石」 四国霊場第24番札所「最御崎寺」の境内に置かれた「鐘石」は、空海の七不思議の一つと呼ばれる石。硬い石質安山岩で上部にデコボコと窪みがあり、叩くと、鏡のような音が響きます。この音は冥土まで届くといわれています。 ●場所 ・・・ マップ |
御厨人窟 今から約1200年前、弘法大師(空海)が阿波の大滝獄から来て、難行苦行を重ねて虚空蔵求聞持法を修められ、かの有名な三教指帰の悟りを開かれたと伝えられる由緒ある海食洞(波の力によって削られた洞窟)です。 神明くつ(東のくつ)みくろど(西のくつ)。 みくろどの中にあるお社は五所神社と呼ばれています。 みくろどの中で聞こえる波の音は「日本の音風景百選」に選ばれています。 法性の室戸といえば我が住めば 有為の浪風よせぬ日ぞなき 空海 これは、弘法大師が当時の苦行を歌ったものです。 ●場所 ・・・ マップ |
 ビシャコ巌 この巨大な巌lこは悲しい伝説があります。 昔この附近に「おさご」と呼ばれた美人が住んでいました。その余りの美しさに多くの男達が朝夕この所に舟を漕ぎよせて来て彼女に愛を求めようとしました。彼女はその煩しさに耐えかねて遂に美女が生まれないように祈 りながら巌頭より投身したと伝えられています。が、「おさご」の命をかけての願いも空 しく、その後も室戸には沢山の美人が生まれています。 ●場所 ・・・ マップ |
 天 狗 巌 海側から見て左側から眺めると、天狗の顔に見えます。 ●場所 ・・・ マップ |
 あこう林 あこうは、亜熱帯植物で室戸岬一帯に自生し、タコの足のような気根を垂れ、岩肌を抱きしめて奇観を呈しています。遊歩道にはその特徴がよく見られ、天然記念物に指定されています。 ●場所 ・・・ マップ |
 月見ヶ浜 その名の通り月の名所。朝日が美しいことでも知られています。 ●場所 ・・・ マップ |
 弘法大師 行水の池 弘法大師が修行中この池で行水されたといわれています。この附近は特に景色がすばらしい。 ●場所 ・・・ マップ |
乱礁遊歩道 奇岩が連なる乱礁遊歩道 奇岩が連なる乱礁遊歩道乱礁遊歩道では、奇岩に荒波が打ち寄せる豪快な風景が見られます。左の写真は「おさご」という美しい娘の伝説が残る「ビシャゴ巌」。  ◆目洗いの池 ややひし形の小さな池。この池にたたえられた水を加持し、人々の目の病気を癒したと伝えられています。近くに、女性が小石を投げ入れると子を授かるという、子授けの岩もあります。  ◆枕状溶岩(まくらじょうようがん) 古い時代に玄武岩質の溶岩が海底で噴出して、枕のような形になりつぎつぎに重なってできたもの  ◆ホルンフェルス(熱変成岩) マグマによって砂岩や泥岩が焼かれて性質を変えたもの。ち密で非常に固い。黒い脈状の岩石はマグマが急に冷えてかたまった玄成岩。  ◆漣痕(れんこん) 海底の妙の表面に流れによってできた模様。「リップルマーク」という。波によって揺れ動くものは比較的浅い砂質の海底にできやすい。流れの方向に向かってゆるやかな斜面をもつ。  ◆砂岩泥岩互層(さがんでいがんごそう) 海底でつもったのが乱泥流という地滑をくり返して、砂の部分と泥の部分に分かれ、交互に重なって再堆積してできたと考えられている。白くとび出しているのが砂岩、黒くくぼんでいる部分が泥岩。  ◆斑れい岩(はんれいがん) 深成岩の一種。白い鉱物は斜長石、黒い鉱物はカンラン石と輝石で、鉱物の大きさは1mm〜数cmまであって、マグマの冷え方が違うことがわかります。室戸岬の先端部にあって平均200メートルの厚さで分布している。また現地では明星石と伝えられています。  ◆砂岩岩脈(さがんがんみゃく) 砂岩泥岩互層を横切るように進入した砂岩の脈。これは地震のとき液状化によって注入されてできたものである。地震の化石。 ●場所 ・・・ マップ |
 夫 婦 岩 夫 婦 岩室戸阿南海岸国定公園の中にあり、室戸岬町と佐喜浜町の境の鹿岡鼻にあり、海中から直立する2つの岩柱は、しめ縄でしっかりと結ばれ、まるで夫婦が連れ添っているようで人目をひく。 多年の風触作用による蜂の巣構造と風紋は美しい。 ●場所 ・・・ マップ |
 ハイビスカス通り ハイビスカス通り亜熱帯植物に属するアコウ・ハイビスカスに温暖な室戸の気候を見ることができます。全長1.1kmにわたり7,500本の植栽されており、6月〜11月中旬に真紅の花が見事に南国情緒をかもしだします。ハイビスカスの北限が室戸岬といわれている。 ●場所 ・・・ マップ |
 室戸ドルフィンセンター 室戸ドルフィンセンター水族館でもないのに、かわいいイルカがすぐ目の前で芸をしてくれる・・・室戸岬新港では、そんな意表をつくシーンに出会えます。エサやり体験にトライ。イルカに触ったり、キスされたりのチャンス!イルカの持つ不思議なパワーをたっぷりいただこう! ◆ドルフィンセンターでは、給餌体験やその他、ドルフィンクラスやドルフィンスクールなど、実際にイルカに触れることができる。 ※但し事前に申込書に記入  《見る=ハロードルフィン》 自由に遊ぶイルカを間近で見られます。 ●実施時間 : AM10:00 〜 PM4:00 ●料金 : 大人(中学生以上) 420円 子供(4歳以上) 315円 4歳未満のお子様は無料 1団体15名様以上、お1人様50円割引 ●参加条件 : 4歳未満のお子様は保護者同伴 ※こちらのプログラムの予約はいりません。 当日受付にてチケットをお買い求めください。  《触る=ドルフィンタッチ》 《触る=ドルフィンタッチ》めったに触れることのできないイルカにタッチができます。イルカのどこにタッチできるかは当日のお楽しみ、イルカの肌の感触はどんな感じか実感できます!! ●実施時間 : 所要時間 約10分 AM10:00 〜 (AM 9:50集合) PM12:00 〜 (AM11:50集合) PM 2:00 〜 (PM 1:50集合) PM 4:00 〜 (PM 3:50集合) ●料金 : 大人(中学生以上) 735円 子供(4歳以上) 630円 ●参加条件 : 4歳以上のお子様は受付にてお申し出ください ●注意事項 : 先着順ですので夏季(特にお盆など)は混雑する場合があります。 当日のチケットは何時の分でもお買い求めいただけます。 定員になり次第、受付を終了させていただきます。 ※こちらのプログラムの予約はいりません。当日受付にてチケットをお買い求めください。  《泳ぐ=ドルフィンスイム》 《泳ぐ=ドルフィンスイム》ウェットスーツを着てイルカの仲間入り、様々な遊びを通してコミュニケーションをとりながらイルカと友達になろう。トレーナーが一緒に入りますので泳ぎの苦手な方でも安心して参加できます。同じ目線で泳いでみませんか。 ●実施時間 : 所要時間 40分 / 各時間定員6名 AM10:20 〜 (AM10:50集合 / AM11:00終了) PM12:20 〜 (PM12:00集合 / PM 1:00終了) PM 2:20 〜 (PM 2:00集合 / PM 3:00終了) ●料金 : 3月〜10月 大人(中学生以上) 8,400円 子供(小学生以上) 5,250円 11月〜2月 大人(中学生以上) 6,300円 子供(小学生以上) 4,200円 ●参加条件 : 小学生以上(身長110cm以上)※お子様だけでも参加できます。 ●持ち物 : 水着・タオルをご持参下さい。 ●注意事項 : 料金にはウェットスーツ一式のレンタル料が含まれています。 簡易更衣室(シャワー付き)がございます。 ※ウェットスーツ(長袖・長ズボン)をお持ちの方はお問い合わせ下さい、レンタル料金を割引できます。 ●事前予約が必要です。  《通じる=トレーナー体験》 トレーナーによるレクチャーで、イルカのお勉強、サインを出してイルカとコミュニケーションが体験できます。餌をあげたり触ったり、イルカと存分に楽しめます。 ●実施時間 : 所要時間 20分 / 各時間定員8名 AM11:20 〜 (AM11:10集合) PM 1:20 〜 (PM 1:10集合) PM 3:20 〜 (PM 3:10集合) ●料金 : 3月〜10月 大人(中学生以上) 2,100円 子供(5歳以上) 2,100円 ●参加条件 : 5歳以上 ●持ち物 : タオルをご持参下さい。(水しぶきがかかる場合があるため) ●事前予約が必要です ※天候やイルカの体調等により、プログラム内容や実施時間を変更する場合があります。お越しの際はお問い合わせ下さい。 お問い合わせ・・・室戸ドルフィンセンター TEL 0887−22−1245 ●場所 ・・・ マップ |
| シレストむろと 室戸海洋深層水体験センター 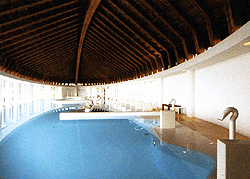 悠久の時をかけて地球の深海を巡り、室戸岬沖海岸から、約2km先の陸棚の切り立った壁にぶつかり湧昇してきた水。それが室戸海洋深層水です。その富栄養性・清浄性・低温安定性などから、底知れぬパワーを持つ水として、加工食品、産業利用など様々な可能性が期待されています。近年健康・美容ブームにマッチする貴重な存在としても注目が集まっています。メタボリックシンドロームや生活習慣病の予防改善に、地元でも人気の施設です。ドイツの伝統的な温浴療法をモデルにした温浴プール、もちろん室戸海洋深層水100%。水温は約34度に保たれ、アクアマッサージや水中ウォーキング、ストレッチが楽しめます。本格派フィンランドサウナや深層水のホットジャグジーも設置。 悠久の時をかけて地球の深海を巡り、室戸岬沖海岸から、約2km先の陸棚の切り立った壁にぶつかり湧昇してきた水。それが室戸海洋深層水です。その富栄養性・清浄性・低温安定性などから、底知れぬパワーを持つ水として、加工食品、産業利用など様々な可能性が期待されています。近年健康・美容ブームにマッチする貴重な存在としても注目が集まっています。メタボリックシンドロームや生活習慣病の予防改善に、地元でも人気の施設です。ドイツの伝統的な温浴療法をモデルにした温浴プール、もちろん室戸海洋深層水100%。水温は約34度に保たれ、アクアマッサージや水中ウォーキング、ストレッチが楽しめます。本格派フィンランドサウナや深層水のホットジャグジーも設置。※当施設は、水中運動やウォーキングでのご利用を目的としており、遊泳用のプールはございません。あらかじめ、ご了承お願いします ●室戸海洋深層水のおもな特性 《低温安定性》  海洋深層水は光の届かない深海にある為、年間を通じて温度が低く、水温は表層水よりかなり低く約9〜9.5度と、とても安定しています。このような特徴を生かし、産業や医療等、様々な分野での研究や利用も盛んになっています。 海洋深層水は光の届かない深海にある為、年間を通じて温度が低く、水温は表層水よりかなり低く約9〜9.5度と、とても安定しています。このような特徴を生かし、産業や医療等、様々な分野での研究や利用も盛んになっています。《富栄養性》 海水には自然の恵みであるたくさんのミネラルが含まれています。海洋深層水にはマグネシウムやカルシウムといった約60種類ミネラルとともに、植物プラクトンの成長に必要なチッ素やリン・ケイ酸などの無機栄養塩が表層水の約5〜6倍含まれています。 《清浄性》 海洋深層水は、現代の産業排水や生活排水、そして河川の影響をほとんど受けたことがなく、生物学的に見ても、高い清浄性を持っています。安心して使える、最も優れた海水の一つです。 ◆営業時間 : AM10:00 〜 PM9:00(季節により変動あり、要確認) ◆休業日 : 水曜日 ◆利用料金 : 一般 大人 1,400円 会員 1,100円 小人(4歳〜小学生) 500円 室戸市民 : 大人 900円 会員 700円 小人(4歳〜小学生) 500円 入浴のみ : 500円 フリーパス券 : 1ヶ月 5,500円 6ヶ月 32,000円 レンタル料 : タオルセット 200円 水着 300円 ※500円で年会会員になれば入場割引の特典があります。 ◆レストラン営業時間 : AM11:00 〜 PM3:00(オーダーストップPM2:30) ◆売店営業時間 : AM10:00 〜 PM9:00 ※深層水商品をはじめ、お土産や地域の物産、美容用品など取り揃えています ◆HP : http://www.searest.co.jp/ お問合せ先 : シレストむろと tel (0887)22-6610 ●場所 ・・・ マップ |
 ホエールウォッチング ホエールウォッチング室戸岬沖は、何種類ものクジラの通り道と言われ、大海原でのホエールウォッチングが楽しめます。全長18mにも達する世界最大の歯クジラ、マッコウクジラが生息。ひと味違う迫力満点のホエールウォッチングが堪能できます。愛嬌たっぷりのイルカなどに出会えるチャンスが、大きな感動に包まれること請け合いです。 マッコウクジラがよく見られる時期は、3月〜5月。 このシーズンなら、ウォッチング成功率70〜80%にのぼるという。  ◆通年、要予約 申し込みは、長岡友久さん宅 TEL 0887−27−2572 山下明博さん宅 TEL 0887−23−0190 ●場所 ・・・ マップ |
吉良川町レトロな町並み
明治中期〜昭和初期にかけて、商業の町として栄えた吉良川町
その頃の商家や建物が今も残され、一歩足を踏み入れると、
まるで当時にタイムスリップしたかのよう!
 吉良川の町並み 吉良川の町並み明治中期から昭和初期にかけて、良質な土佐備長炭の積み出し港として栄えた吉良川。海岸に近い下町には回船問屋や米穀商、炭屋など商家も多く、往時をしのぶレトロな町並みが残っています。切妻造りで土佐漆喰の白壁や、水切り瓦、「いしぐろ」と呼ばれる石垣など、どれも美しく、土佐の厳しい気候風土に対応した建築様式。そぞろ歩くだけでも、昔懐かしいひとときに浸ることができます。  なおこの町並は高知県で初めて、国の重要伝統建造物群保存地区に選定されています。保存会によるボランティアガイド案内もあります。(要予約) なおこの町並は高知県で初めて、国の重要伝統建造物群保存地区に選定されています。保存会によるボランティアガイド案内もあります。(要予約)《水切り瓦》 土佐独特の強い雨風などから、家屋を守る。幾重ものひさしが、壁面に直接雨がかかるのを防ぎ、漆喰の白壁を保護します。 《いしぐろ》 台風などの強風から家を守る暴風石垣塀。浜石や河原石を丸のまま、または半割にして、空積みにしたり、練り積みにしたりと家々で微妙に異なっています。  ◆吉良川町並みガイド(要予約) 料金 : 5名以下 1,000円/回 6名以上 200円/人 1団体(バス1台) 3,000円/回 お問合せ先 : 吉良川町並み保存会 tel (090)8978-4516 吉良川まちなみ館 tel (0887)25-3670 ●場所 ・・・ マップ |
吉良川の町並み館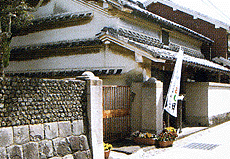 吉良川の昔ながらの家です。館内には町並み散策パンフレットを置いてあり、又季節により展示物が異なり ますので、1年中楽しめます。気軽にお立ち寄り下さい。 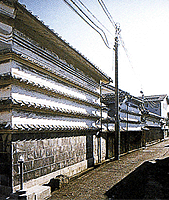 《松本家住宅》 松本家では、街道の角に表蔵が設けられています。表蔵は街道に妻側を見せ、腰壁に瓦が平目地で貼られています。この地に二つの蔵があり、米蔵や長持ちなどを入れる蔵として使用されました。主屋の建築年代は明治時代中期と推定されます。  《武井家住宅》 明治44年に建築された武井家は米穀商いを商うとともに遠洋漁業も手がける商屋でした。武井家の主屋には建築的な特徴が多く見られます。平屋・つし二階、二階が混合した建て方で変化のある外観を見せ、妻壁の仕上げにはふんだんに煉瓦が用いられています。煉瓦は京阪神からの帰りに、船の底に積んで持ち帰ったもので、西洋文化の香る煉瓦の外壁は吉良川に近代の新しい風を吹かせました。 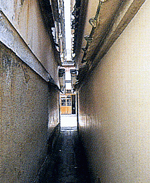  《細木家住宅》 《細木家住宅》主屋は、明治39年に建てられました。田の字型の間取りを構成し、主屋正面右側には隣家と共通の内路地があります。敷地内には二つの蔵や、二階に座敷のある離れなど、明治期の敷地利用の形態が良く保たれています。細木家は現在も備長炭を商う商屋です。  “備長炭” 大正期から昭和期にかけて、吉良川の繁栄の基盤となったのが備長炭です。吉良川近隣で産出する樫や馬目樫は、近世期に薪として京や大阪で好んで用いられていました。良質で火力が強く製炭にも適していることから、これらを素材に明治10年頃から木炭の製造が始まりました。  《細木家住宅》 吉良川八幡宮参道の東側の角に建つ細木家は、明治42年に建築されました。初代は呉服業を営んでいました。当家は明治中期の建築様式を良く残し、外観にも特徴があります。主屋はつし二階建てで道に面した2室はミセとよばれています。座敷庭が設けられ風呂や便所へは太古橋状の渡り廊下でつながれています。  《池田家住宅》 炭問屋を営んでいた池田家は、店(マエノニカイ)、門(ホンモン)と両脇の塀、蔵(コメグラ)により構成されています。蔵や店の腰壁は海鼠壁を用い、主屋は店と玄関によって複雑につながり、離れは渡り廊下で結ばれています。これらの形成は関西地方の「表屋造り」の構成と共通しており、備長炭の回船により伝えられた建築文化だと考えられます。  《仙頭家住宅》 明治時代に建築された仙頭家は、今も石垣に囲まれて懐かしい佇まいを見せている上町に残された伝統的民家です。路地に面した妻壁は幅の広い美しい下見板貼りです。仙頭家の前面にある竹垣といしぐろは台風時の防風用に設けられています。  《御田八幡宮》 《御田八幡宮》吉良川町上町に鎮座する御田八幡宮は古い歴史を持ち、人々の信仰の中心となってきました。祭神は誉田天皇、神功皇后、比羊神であり境内には八坂神社や稲荷神社があります。秋の神祭の花台は上町、東町、下町(中町)、西町の順に町を進みますがこれは町が形成された順に従っているといわれています。西暦奇数年5月3日に行われる御田祭では鎌倉時代から伝わる田楽、猿楽の芸能が奉納されます。  《木下家住宅》 《木下家住宅》いしぐろに囲まれて建つ木下家は、明治時代には隠居家として使用されていた建物だったようです。基本的には2室構成で、部屋の三方には差鴨居が回された素朴な造りとなっています。以前は土間の脇にブッチョウ(揚見世)があり、駄菓子が売られていました。 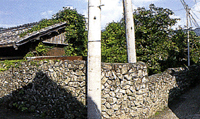 《いしぐろの見える道》 春風や花火のはねる夏の夕方、子どもたちが駆け巡り花台が繰り出す秋、大晦日の夜、いしぐろの路地は故郷の優しい風景です。 “いしぐろ” 吉良川町では、台風などの強風から家を守るために、いしぐろとよばれる石垣塀を民家の周辺に築いています。これらは玉石や半割り石を空積みや練積みといった方法で造られています。     《いしぎろに囲まれた民家》 《いしぎろに囲まれた民家》吉良川のいしぐろの石は浜石と河原石です。川に運ばれた土佐湾に沈んだ石は黒潮と台風などの激しい海流によって吉良川の海岸に打ち上げられたのでしょう。上町でもいしぐろに囲まれた民家が多く見られます。強風から家を守る防風石垣塀は家々で微妙に異なったデザインを見せ、地域の景観を個性的に印象づけています。  《上町の井戸》 下町では、屋敷内に井戸を持つ民家が多く、水を得にくい上町では限られた井戸を共同で使い、管理することが多かったようです。共同の井戸は水道が普及するまで隣近所の人々の交流の場所でもありました。  《熊懐家住宅》 《熊懐家住宅》熊懐毛は、大正11〜12年に建てられた洋風建築で、昭和40年頃まで郵便局として使用されていた建物です。鬼瓦には、郵便局であることを示す「〒」マークが施されており、とてもユニークです。 ※上記説明の商屋・建物に関しての地図案内はありません。吉良川町並み館に 散策パンフレットがありますので、そちらのパンフレットを参考にしてください。 ◆吉良川町並みガイド(要予約) 料金 : 5名以下 1,000円/回 6名以上 200円/人 1団体(バス1台) 3,000円/回 お問合せ先 : 吉良川町並み保存会 tel (090)8978-4516 吉良川まちなみ館 tel (0887)25-3670 ●場所 ・・・ マップ |
 |
高知県観光ページへ 愛媛県観光ページへ 香川県観光ページへ 徳島県観光ページへ