第 284 号 |
| 中岡慎太郎館訪問 |
6月20日何度目かに中岡慎太郎資料館の訪問で有る、何故私は中岡慎太郎資料館を何度も訪問するかと言われる人も居ますが、中岡慎太郎ぐらい民を思い、地域を思い、国の為に私心を捨てて、大きな志で行動し続けた人物は他には居ないのでは無いかと思うからです、志、素直、知識、知恵、を持ち自分を捨てて他人の為に行動し、地域を思い、国を思う行動に深く感銘するからです、もし此の記事を読んで疑問に思う人が居たなら、一度資料館に行ってみてください凄い人間味が解ると思います。以下は中岡慎太郎の行動の一部ですが、中岡慎太郎資料館文献を参考に紹介致します。 【中岡 慎太郎(なかおか しんたろう)】 天保9年4月13日(1838年5月6日)慶応3年11月17日(1867年12月12日)。幕末の代表的志士の一人であり陸援隊隊長。名は道正。変名に石川清之助(誠之助)などがある。 中岡慎太郎は、土佐国安芸郡北川郷柏木村(現・高知県安芸郡北川村柏木)に北川郷・大庄屋の長男として生まれる。幼少時より俊才の誉れ高く、18歳のころ武市瑞山(半平太)の道場に入門し、その後、武市が結成した土佐勤皇党に加盟して、本格的に志士活動を展開し始めた。 文久3年(1863年)京都での八月十八日の政変後に土佐藩内でも尊王攘夷活動に対する大弾圧が始まると、土佐藩を脱藩し、同年9月、長州藩三田尻(現防府市)に亡命。以後、長州藩内で同じ境遇の脱藩志士たちのまとめ役となり、三田尻に都落ちしていた三条実美の衛士となるなど長州をはじめとした各地の志士たちとの重要な連絡役となっていった。 元治元年(1864年)石川誠之助を名乗り上洛。薩摩藩の島津久光暗殺を画策したが果たせず、また脱藩志士たちを率いて禁門の変、下関戦争を長州側の立場で参戦し、負傷。長州藩への冤罪・雄藩同士の有害無益な対立・志士たちへの弾圧を目の当たりにして、活動方針を単なる尊皇攘夷論から雄藩連合による武力倒幕論に発展させる。そして、龍馬を含む誰よりも早く、長州藩の桂小五郎(木戸孝允)と薩摩藩の西郷吉之助(西郷隆盛)との会合による薩長同盟締結を倒幕のための第一の悲願として活動し始めた。 有力公家の三条実美とも連絡を取りつつ脱藩志士たちのまとめ役として、薩摩と長州の志士たちの間を飛び回り、海援隊の坂本龍馬や三条の随臣を説得、活動に巻き込んで行き、慶応2年(1866年)1月、京都二本松薩摩藩邸において薩長同盟(薩長盟約)という歴史的転換点を結実させる事に成功した。 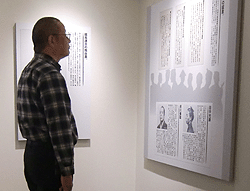 その後、薩土同盟についても同様に東奔西走し、薩摩藩と土佐藩との間で、倒幕・王政復古実現のための薩土盟約が締結される。この盟約は長州藩の隣の安芸藩を加えた薩土芸三藩約定書に拡大発展。土佐藩を戊辰戦争において薩摩・長州・肥前と並ぶ倒幕の主要勢力たらしめ、その結果として土佐藩出身者を薩摩、長州、肥前出身者同様に幕末・明治をリードする主要政治勢力たらしめた。その後、長州の奇兵隊を参考に、自身を隊長とする陸援隊を京都に組織。また、この頃に討幕と大攘夷を説いた『時勢論』を著している。 その後、薩土同盟についても同様に東奔西走し、薩摩藩と土佐藩との間で、倒幕・王政復古実現のための薩土盟約が締結される。この盟約は長州藩の隣の安芸藩を加えた薩土芸三藩約定書に拡大発展。土佐藩を戊辰戦争において薩摩・長州・肥前と並ぶ倒幕の主要勢力たらしめ、その結果として土佐藩出身者を薩摩、長州、肥前出身者同様に幕末・明治をリードする主要政治勢力たらしめた。その後、長州の奇兵隊を参考に、自身を隊長とする陸援隊を京都に組織。また、この頃に討幕と大攘夷を説いた『時勢論』を著している。慶応3年(1867年)12月、京都・近江屋にて坂本龍馬を訪問中、何者かに襲撃され、瀕死の重傷を負う(近江屋事件)。龍馬は即死状態であったが、慎太郎は2日間生き延び、暗殺犯の襲撃の様子について谷干城などに詳細に語った後に絶命した。享年30であった。以下は中岡慎太郎の足跡を年代ごとに詳しく紹介致します。 中岡慎太郎は天保9年(1838年)4月、高知県安芸郡北川村柏木(北川郷柏木村)の中岡小伝次の長男として生まれた。幼名は福太郎。 慎太郎の父・小伝次は高知県東部第一の人物として知られる大庄屋であり、それまで男児に恵まれていなかった中岡家にとって待望の長男であった。それだけに慎太郎の教育には特に熱心になされたいう。 3歳の時、名を光次(こうじ)と改め、父から読み書きの指導を受けはじめ、4歳になると生家付近にある松林寺の住職・禅定和尚に読書を学び、7歳になると鳥ケ森を越して片道1時間半近くの山道を歩き、漢方医・志摩村策吾の塾に入塾して「四書」を学んだ(「四書」とは儒教経典の一つで「論語」「大学」「中庸」「孟子」の4つをまとめた呼び方) 慎太郎が14歳の時に、母が病で亡くなったものの、その年にして島村塾で代理で講師として講義をするほど立派に成長していた。また、後に書道の達人となる慎太郎は、このころに安田の乗光寺というところで書も学んでいる。 その翌年には、土佐文武の先覚者と言われ名を成していた間崎滄浪(哲馬)に自ら願い出て師事。詩書(中国の詩経と書経)を学ぶなど熱心に勉学を行っている。 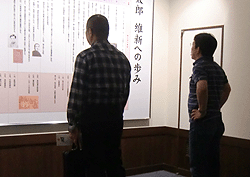 幼少時の慎太郎のエピソードでこんなものがある。 幼少時の慎太郎のエピソードでこんなものがある。ある夏のこと、数名の友人と柏木の巻の渕というところへ泳ぎに行った時のこと。底が見えない渕は青々として、そのうえ常に大きな渦が巻いているので人々からその渕には入ってはいけないと言われている場所だった。ところが慎太郎は林を通って20メートル近くある断崖の上へ現れたかと思うと、身を躍らせて頭から飛び込み、何事もなかったかのように浮上してきた。それを見た大人たちは慎太郎の肝の太さに感嘆し、豪胆な少年として噂しあったという。まさに文武  両道の英才として、幼少期からその片鱗を見せていた。 両道の英才として、幼少期からその片鱗を見せていた。安政元年(1854年)中岡慎太郎17歳。 ペリーが初めて浦賀に来航した翌年であるこの年、高知城下だけであった藩校が郡で初めて設置されると、慎太郎はただちに田野学館に入学。この田野学館に近隣の有志が多く通っており、清岡道之助、その弟・半次郎らをはじめ、多くの有志と交わりを持つことができた。(清岡道之助は、後に勤皇志士として苛烈な思想に傾倒してゆくようになり、やがては単独で強行的手段を選択。ついに元治元年(1864年)7月、配下・門弟の23名を従えて岩佐番所を本陣として挙兵。その後、鎮圧され斬首されることとなるいわゆる「野根山二十三士殉節」の首領。中岡はその報を聞き、大いに嘆き悲しんだ。この報を聞いた中岡は土佐の同志に「天下挽回再挙なきにあらず、然りながら今暫く時を見るべし。依りて沸騰及び脱藩は甚だ無益なり。涙を抱えて沈黙すべし。他に策なし」という悲痛な自重を求める手紙を送っている) 安政2年(1855年)、田野学館に藩命により、後に土佐勤皇党の首領となる武市瑞山(半平太)が出張してきて、慎太郎も武市に剣術を学んだ。その際、武市瑞山の人格と武術に敬服し、武市が高知に帰った後、あとを追うように慎太郎も高知に出て武市瑞山の道場に入門。 翌年3月には、郷士の小者として土佐を出国、江戸の三大道場のうちの一つである「鏡新明智流」の桃井春蔵の門下生として剣術修行に励んでいる。その後、5月には土佐藩砲術指南の吉村賢次郎の塾にも入門。文武両面ともに様々な分野・学問を吸収する中岡慎太郎の向学心には目を見張るものがある。 安政4年(1857年)、慎太郎が20歳の時、父・小伝次が病気になったという知らせが届き9月に郷里である柏木に帰り、北川郷大庄屋見習となった。その後、父の言葉に従い野友の庄屋・利岡彦次郎の長女であった兼(かね)15歳と結婚する(国事に奔走することになる慎太郎と兼とが安穏とした夫婦生活を送れるはずもなく、二人の間に子供は出来ていない) 大庄屋見習となった慎太郎は農民のために活躍。安政元年、安政2年に起こった2回の大地震や風水害の被害、疫病の流行で困窮していた村人たちを救うべく次々と抜本的な復興策を打ち出していった。 山林を整理し、木を切ったあとへは必ず植林をさせ、また田畑の開墾をすすめ、高知から作物の優良品種を取り寄せる耕作の指導を行い、同時に飢饉や災害の時のために貯蓄をさせるなどもした。現在、高知県北川村の特産となっている「ゆず」を屋敷のまわりや山すそに植栽するよう推奨したのもこの頃で、塩を買うことができなくとも川魚を採ってくればゆずをかけることにより食べることができるという、飢饉対策の一環だった。 また、飢饉が起きた際は高知城下に出て、直接国老の桐間蔵人に直訴。鬼気迫る陳情を行い、桐間に官倉を開かせ、村民を救済することに成功したという(この時の恩を忘れられない村民たちは、明治に入り北川村小島に中岡の顕彰碑を建てている) その後、慎太郎が24歳の時、敬服する武市半平太が土佐勤皇党を立ち上げ、慎太郎もそれに加わるまでの間、庄屋として農民のために尽力し続けた。文久元年(1861)8月、武市瑞山が結成した土佐勤王党の血盟文に17番目に署名。志士としての活動をスタートさせる。中岡慎太郎、時に24歳。 翌年10月、五十人組結成に参加(五十人組とは、勅使・三条実美が江戸へ下る際、土佐藩主・山内豊範がこれを護衛することになり、豊範の江戸参勤に随行できなかった土佐勤王党の同志たちが島村寿之助らの資金援助をえて結成された警護部隊のこと) 11月には前藩主・山内容堂の守衛の藩命を受けて江戸に行き、長州の俊英・久坂玄瑞と水戸で交わり、さらに信州松代の佐久間象山も訪問している。 慎太郎は「松下村塾の双璧」と言われ、高杉晋作とともに松下村塾を代表する門下生であった久坂玄瑞と交わる中で、松下村塾の主宰者・吉田松陰を深く尊敬するようになる。吉田松陰は安政の大獄により斬首されており、すでにこの世にいなかったが、慎太郎は吉田松陰を亡き師として終生尊敬し、松陰の教えを行動の指針としていくようになる。 中岡慎太郎は、いわゆる松下村塾の門下生にはあたらないが、精神的な「松陰門下」と言うことができるかもしれない。 文久3年(1863年)七月、板垣退助と会合し意気投合(板垣退助とは薩土盟約締結の際、行動を共にすることとなる) 同年、京都で「八月十八日の政変」が起こり、土佐藩内でも尊王攘夷活動に対する大弾圧が始まると、土佐藩を脱藩。長州藩三田尻(現防府市)に亡命する。以後、長州藩内で同じ境遇の脱藩志士たちのまとめ役となっていく。また、三田尻に都落ちしていた三条実美の随臣となり、長州をはじめ各地の志士たちとの重要な連絡役ともなる。この間、招賢閣会議員にもなっており(招賢閣とは、三条実美をはじめ七卿が都落ちをして来た時の宿所であり、脱藩の志士達の議論の場となった場所)、尊攘派浪士たちの指導的役割を担う志士として、本格的な活動を行っていった。 元治元年(1864年)、上京して長州藩邸に入り、高杉晋作、久坂玄瑞らとともに活動。儒者・中沼葵園の塾に入門し、中村半次郎(後の桐野利明)など薩摩の尊攘派志士たちとも交わっている。その後、高杉晋作らと薩摩藩の島津久光暗殺を画策したが果たせず、長州・三田尻へ戻る。 同年6月に再び上京。前年の「八月十八日の政変」で京都政界を追放された状況を挽回しようと、暴発する形でついに京へ武力行使に至ることになってしまった長州藩の戦いに加わる。いわゆる「禁門の変」である。 慎太郎は、郷里の家族に遺書を認め遊撃隊に加わり、激闘。足を負傷し退く。8月には、四国連合艦隊の「下関」攻撃に対し、忠勇隊としても出陣。後に忠勇隊隊長にも任命されている。この頃より、長州藩への冤罪・雄藩同士の有害無益な対立・志士たちへの弾圧を目の当たりにして、活動方針を単なる尊皇攘夷論から雄藩連合による武力倒幕論に発展させていくこととなる。 そして、誰よりも早く雄藩である薩摩と長州の協力関係の必要性を語り、長州藩の桂小五郎(木戸孝允)と薩摩藩の西郷吉之助(隆盛)との会合による薩長同盟締結を志士たちの第一の悲願として活動し始めた。 単なる尊皇攘夷論から雄藩連合による武力倒幕論に発展させていくことの必要性を痛切に感じ、誰よりも早く、雄藩である薩摩と長州の協力関係の必要性を語り、長州藩の桂小五郎(木戸孝允)と薩摩藩の西郷吉之助(隆盛)との会合による薩長同盟締結を第一の悲願として活動し始めた中岡慎太郎。 中岡の志士としての活動の真骨頂がここから始まる。 元治元年(1864年)11月、筑前の早川養敬が馬関に来たのを機に、薩長同盟の急務を説く。同年12月、幕府の長州征伐について小倉で薩摩の西郷隆盛と会談(実質的な薩長連合の画策の始まりと言える)。さらに馬関で西郷と高杉晋作の会見を実現させる。その後も、長州藩、薩摩藩、両藩のビッグネーム、有志を中心に薩長和解の遊説を精力的に行っていく。 慶応元年(1865年)1月、長府で高杉晋作と山縣狂介(後の山縣有朋)と会談。2月には長州藩有志に対し薩長和解の説得を行い、京の薩摩藩邸にも出入り。4月には下関にて村田蔵六(後の大村益次郎)、伊藤俊輔(後の伊藤博文)と面談。同月に長州藩尊攘派のリーダーと言える桂小五郎(後の木戸孝允)と面会し、薩長同盟について打診している。 同年5月、薩摩(鹿児島)に入り西郷隆盛に上京の途中で長州への立ち寄りを説き、西郷隆盛とともに薩摩を出港。しかし、途上で「急用あり。大坂へ急げ」との藩命を受け西郷は約束を果たさずに大坂へ向かってしまう。慎太郎は失意のうちに単身下関に帰着。それでも慎太郎はあきらめない。  6月、坂本龍馬と共に京都の薩摩藩邸に滞在して薩長和解の策を練る。7月、田中顕助上京。慎太郎の説に大いに賛同し、田中顕助と京都より長州へ出発。さらに薩長両藩和解の利害を諸隊に説く。8月、薩長和解問題解決のため、単身上京。その後も京、長州、太宰府などを活動のために往復している。 6月、坂本龍馬と共に京都の薩摩藩邸に滞在して薩長和解の策を練る。7月、田中顕助上京。慎太郎の説に大いに賛同し、田中顕助と京都より長州へ出発。さらに薩長両藩和解の利害を諸隊に説く。8月、薩長和解問題解決のため、単身上京。その後も京、長州、太宰府などを活動のために往復している。11月、「時勢論」を記す。「自今以後、天下を興さん者は必ず薩長両藩なる可し、吾思ふに、天下近日の内に二藩の令に従ふこと鏡にかけて見るが如し、他日本体を立て外夷の軽侮を絶つも、亦此の二藩に基づくなる可し」(「これから天下は薩摩、長州の二藩の命に従うようになる」との見解、「薩摩、長州ともに外国と戦い、敗れたことで民族の独立を意識するようになった」と述べている。また「富国強兵と云ふものは、戦の一字にあり」とも書いている) 翌年の慶応2年(1866年)1月、中岡、龍馬らの尽力により、京の薩摩屋敷にて悲願であった長州の桂小五郎、薩摩の西郷隆盛、小松帯刀の会談が実現。しかし、両藩の面子から双方が薩長同盟の話を切り出さず、一時は破談になりかけた。しかし、同席した坂本龍馬が「窮地にある長州から同盟を申し出ることはできないはずだ。今は藩の面子を気にしている時ではない」旨を西郷に説き、薩摩が申し出る形で決着。最後のひと押しを龍馬が行ったことで、中岡の悲願であった薩長同盟(薩長盟約)は合意に至った。歴史的転換点・薩長同盟が成った後も、中岡は行動を止めない。 その後も同様に奔走し、土佐藩と薩摩藩を結びつけるべく板垣退助に西郷隆盛を紹介し会談させ、倒幕のための薩土密約を実現。更に土佐藩そのものを本格的に取り込むための運動を展開し、慶応3年(1867年)6月、京において、薩摩の小松帯刀・大久保一蔵(大久保利通)・西郷吉之助、土佐の後藤象二郎・乾退助・福岡孝弟らとの間で、倒幕・王政復古実現のための薩土盟約を正式に締結させた。7月、長州の奇兵隊を参考に「陸援隊」を本格的に組織し始め、自ら隊長となり、白川土佐藩邸を陸援隊の本拠地と定める。この頃、討幕と大攘夷を説いた「時勢論」を再び著している。「西洋各国の国勢を見れば、軍備政教を一新して国体を立ててきた。いまだ周旋と議論とに終始して国を興したことは聞かない」「邑ある者は邑を投げ捨て、家財ある者は家財を投げ捨て、勇ある者は勇を振るい、智謀ある者は智謀を尽し、一技一芸あるものはその技芸を尽し、愚なる者は具を尽し、公明正大、おのおの一死をもって至誠を尽し、しかるのち政教たつべく、武備充実、国威張るべく、信義は外国におよぶべきなり」と述べ、後藤象二郎や坂本龍馬の大政奉還論を論難。また薩摩や長州が英国と戦った様子を述べ、国難に際しては、階級に関係なく、民衆が一体となることで藩論が一変したことを説いている。慶応3年(1867年)7月、薩長同盟、薩度盟約締結後も精力的に活動していた中岡慎太郎は、京都白川村の土佐藩邸内に陸援隊を組織し、自ら隊長となり倒幕挙兵への準備を怠らない。そして、大政奉還を策する佐幕公武合体派に対抗して武力倒幕、王政復古のために岩倉具視や西郷隆盛などと会い、画策を続けた。 そして、運命の同年11月15日(西暦1867年12月10日)寒い冬の日のこと。 中岡慎太郎は、三条制札事件で町奉行所に囚われていた土佐藩士の宮川助五郎が釈放されると聞き、その身柄の引き取りについて谷守部の下宿先であった大森方を訪ねた。しかし、谷が不在だったため、夕刻に近くの龍馬の仮寓である近江屋を訪れ話し合いを行っていた。 その日、龍馬は風邪気味で母屋の二階奥の八畳間で北側の床の間を背にして座っており、火鉢をはさみ南面して中岡と対座し、話をしていたという。部屋を隔てた表の間では、龍馬の従僕で元力士の山田藤吉が楊枝をけずっていた。夜9時頃になり、客(刺客)が近江屋を訪れ「拙者は十津川の者だが、坂本先生御在宿ならば御意を得たい」と告げた。十津川郷士には龍馬の知人も多いので藤吉は不審に思うことなく、見知った客か龍馬に確認しようと二階へ上ろうとした。踵を返した藤吉を見て、龍馬がいると確信した刺客たちは後からそのまま藤吉の背中を斬りつけた(翌日に死亡)。このとき「ぎゃあー」と絶叫を上げた藤吉に対し、龍馬は相撲でもとって遊んでいるのかと勘違いしたのか「ほたえな!(土佐弁で「騒ぐな」の意)」と言い、刺客に図らずも自分たちの居場所を教えてしまう。 刺客は音もなく階段を駆け上がり、ふすまを開けて風のように部屋に侵入(この他、浪士達が二人を斬る前に名刺を渡してから斬ったという説などいろいろな説がある) 刺客の一人は中岡に斬りかかり、一人は対座していた龍馬の前頭部を横に斬り付けた。慎太郎は刀を屏風の背後に置いてあったので、短刀の鞘をはらって、敵の懐に飛び込もうとするも、慎太郎は足を切り払われ、思うように応戦ができない。初太刀の痛手に、さらに数創を受けてついに倒れてしまった。 龍馬は初太刀を前額に浴びたものの、とっさに後ろの床の間に置いていた佩刀(陸奥吉行)を取ろうと身をひねったが、右の肩先から左の背骨にかけて大袈裟に斬られた。その後、刀を掴んで立ち上がろうとしたが、刺客の三の太刀が襲い、鞘のままかろうじて受け止めた。だが、敵の斬撃は凄まじく、龍馬の刀身を斜めに削り、その余勢をもって龍馬の前額部を深く薙ぎ払った。脳漿が吹き出す致命傷を受けてしまう。  龍馬は意識がもうろうとする中、中岡の正体がばれないように中岡のことを「石川、太刀はないか」と変名で呼んだといい、その後ついに昏倒、刺客がさった直後に絶命した。 龍馬は意識がもうろうとする中、中岡の正体がばれないように中岡のことを「石川、太刀はないか」と変名で呼んだといい、その後ついに昏倒、刺客がさった直後に絶命した。中岡慎太郎は刺客が去った後も驚異的な生命力で生きており、一時は焼飯を食べるほどとなり、事件の証言も行ったが、出血多量のために次第に衰弱。田中顕助は瀕死の慎太郎の耳に口をよせて「長州藩の井上聞多を見て下さい。刺客により全身を切り裂かれたにもかかわらずまだ生存しています。先生、力を落としてはいけません」と必死の励ましをするものの、慎太郎は死期が近いのを知るかのように後の事を同志に頼みはじめた。「早く倒幕の挙を実行しなければ、却って敵のために逆襲せられる。同志の奮起を望む」という悲痛な遺言を残して、事件から2日後の昼過ぎ、ついに絶命、昇天した。享年30。公卿の岩倉具視は、中岡の絶命を聞くと「自分の片腕をもがれた」と声をあげて悲泣したと云われ、大久保一蔵(後の大久保利通)に宛てた手紙にも「この恨み必ず報ぜざるべからず」としたためており、その痛恨・哀惜の情がうかがえる。 (中岡慎太郎資料館文献参考) |
| 平成27年6月20日 |
| 目次へ |